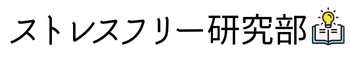日本人のおよそ5人に一人が慢性的な不眠を抱えていると言われる昨今1。ストレスで眠れないのか、眠れないのがストレスなのか、というようなモヤモヤを抱えている人は決して少なくないでしょう。
現在、不眠治療には睡眠薬などの薬物療法が一般的ですが、メンタルヘルス先進国のアメリカでは、「認知行動療法」という精神療法が推奨されている2のだとか。不眠に効果があるとされる「認知行動療法」とは、いったいどういう治療法なのでしょうか。
睡眠薬と認知行動療法、どっちが効くの?
「認知行動療法」とは、ストレスの元になっている考えや行動の癖を見直して、心を楽にしていく心理・精神療法のひとつ。「Cognitive Behavior Therapy」の頭文字を取ってCBTとも言われます。うつ病や不安症、強迫症など幅広い疾患で高いエビデンスが示されており、睡眠障害においてもその有効性が数多く報告されているそうです。
不眠の認知行動療法(CBT for Insomnia: CBT-I)には、どのような特徴があるのでしょうか。日本の標準治療として一般的な薬物療法と比較してみましょう。
- 比較的即効性がある
- 日中の眠気や認知機能の低下などといった副作用がある
- 長期的に使用すると耐性がついて効かなくなってくる
- 服用をやめると元の状態に戻ってしまう
- 効果が出るまでに時間がかかる
- 治療終了後も効果が続き、再発しづらい
- 服用中の睡眠薬を減らしたり中止したりすることができる
- 身体的な副作用がほとんどない
報告書によれば2、CBT-Iによって慢性睡眠障害を抱えている患者の50%が寛解し、70~80%に症状軽減が期待できるとのこと。とりわけ寝付き(SOL)の改善については、薬物療法よりもCBT-Iのほうが明らかに効果が高いことが分かっているそうです。また、すでに睡眠薬を服用している場合、同時にCBT-Iを実施することで睡眠薬の中止率が高まる(CBT-Iを実施しない場合が48%なのに対し、実施した場合は85%の中止率)という報告もあります。
依存性や副作用が問題視されている薬物療法と比べて、CBT-Iは副作用がほとんどなく、また治療後も効果が持続するということですから、現在睡眠薬などの薬物療法を実践している人にとっても、決して少なからぬメリットがあると言えそうです。実際に、アメリカや欧州のガイドライン3では、不眠症治療の第一選択肢としてCBT-Iが推奨されています。
日本でもCBT-Iを受けることができるの?
海外ではすでに認知が広まっているCBT-Iですが、実際のところ日本の医療機関でも受けることはできるのでしょうか。残念ながら、現状における日本での普及率はそれほど高いものではないようです。その理由として最も大きいのは、CBT-Iを実施できる専門家が不足しているということが言えるかと思います。また、まだ保険適用されていないというのも、患者への負担という意味で普及の妨げになっているでしょう。
とは言え、近年日本でも普及の必要性が強く認識されつつあるようですから、提供体制がいち早く整うことを期待したいところです。
CBT-Iを生活に取り入れてみよう
CBT-Iを受けられる医療機関が近くにないという時には、オンラインや電話による治療を検討するのも一つの手かもしれません(その際は、実施者が臨床心理士や公認心理師など信頼できる資格を持っているかどうかを必ず確認しましょう)。対面による治療に比べて効果は劣るものの、Web形式や電話形式でも有効性が認められているそうです4。

加えて、セルフヘルプ形式(専門家を介さずに当事者だけで実践すること)でも治療効果が示されているということで、もしかすると一人でも明日から実践できることがあるかもしれません。せっかくですからここで、CBT-Iの具体的なプロトコル5を学んでみましょう。ここでは簡単に3ステップにまとめました。
① 睡眠日記をつけて客観的に眺めてみる
CBT-Iの目的は、「不眠の原因となっている生活・睡眠習慣や考え方などを明らかにし、修正することによって自然な眠りを取り戻すこと」。まずは、睡眠日記をつけて、自分の睡眠習慣を客観的に眺めてみることから始めます。
日記には、寝床に入った時間、入眠時間、中途覚醒時間、中途覚醒回数、最後に目が覚めた時間、寝床から出た時間などを記録し、そこへ「どれぐらいよく眠れたと感じたか」、「日中の活動にどの程度支障をきたしたか」などの自己評価を加えます。こうして記録するだけで、睡眠と日中の支障や生活習慣が思っていたよりも関連してないことに気づき、不眠症状が軽減する人もいるそうです。
なかなか継続の難しい記録作業ですが、書籍やアプリなどの関連ツールを利用すると無理なく習慣化できるかもしれませんね。
② 睡眠に関する正しい知識を身につける
不眠のメカニズムへの理解を深め、自分自身の生活習慣と照らし合わせてみる工程も大切とのこと。ここでは、いくつかの要素について簡単にまとめてみます。

③ 「睡眠スケジュール法」を実践してみる
①で記録した睡眠習慣を見つめ直し、規則的な睡眠のリズムを再構築するために「睡眠スケジュール法」を実施します。
睡眠スケジュール法
目標睡眠時間は、平均睡眠時間+30分~1時間に設定する
例えば、目標時間が5時間で、毎朝6時に起きる場合は、深夜1時に寝るようにする
あえて早めにベッドに入ったりなどはしないようにする
ベッドから出てリラックスできることをし、眠気を感じたら改めてベッドに入るようにする
日中にできるだけ疲れを貯める
「睡眠スケジュール法」を実施することにより、実際に寝ている時間とベッドで横になっている時間のズレを修正し、「ベッドで横になる=睡眠」という認知を取り戻すことが期待できるのだとか。
まとめ
7~8時間睡眠が理想だとよく言われますが、だからと言って普段4、5時間しか眠れていないのに、いきなり理想の睡眠時間を目指しても、プレッシャーになってむしろ眠れなくなってしまいそうです。その点、15分ずつ目標時間を増やしていくというCBT-Iは、とても地に足のついた治療法だと感じました。
今回はCBT-Iの概要を簡単にまとめましたが、本来は不眠に悩む人それぞれの理由に合わせて治療計画を立てていくものかと思うので、できれば専門家の指導の元で実践したいところ。CBT-Iを気軽に受けられる医療体制が、早く整ってほしいものですね。
- 厚生労働省 令和4年(2022) 国民健康・栄養調査
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r4-houkoku_00001.html - CBT-Iの理論と実践
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/58/7/58_616/_pdf - 欧州不眠症ガイドライン: 不眠症の診断と治療に関する2023年改訂版(日本語訳)
https://yukifurukawa.jp/european-insomnia-guideline-2023/ - 睡眠障害と心理社会支援
https://www.ncnp.go.jp/mental-health/docs/nimh65_37-42.pdf - 不眠の認知行動療法 実践マニュアル
https://www.asakura.co.jp/user_data/contents/30112/1.pdf